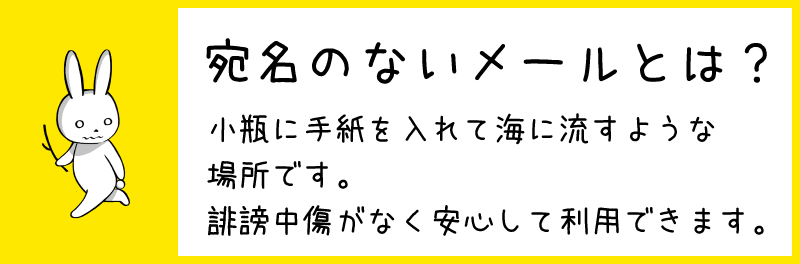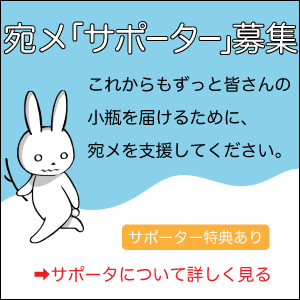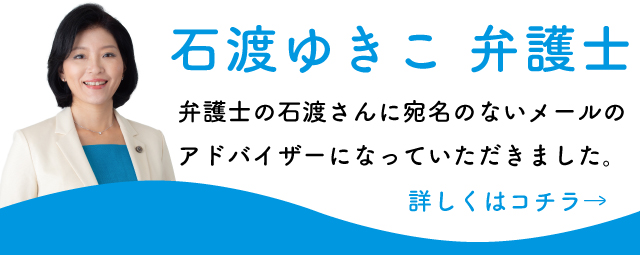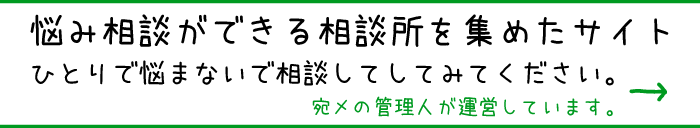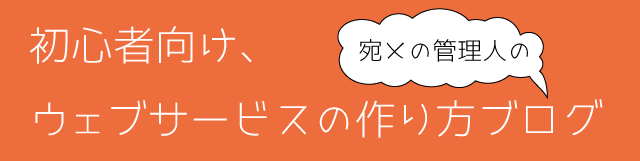大好きだった推しがいた。狂気と知的さの混じった表情も、ひょろひょろした背中も、年齢の割には少し低い声も、ほんとうにほんとうに大好きだった。生きる次元の違いなんて気にならなくて、ただただ憧れで、尊敬で、私の世界だった。
降りた理由は至極単純で、まず運営からの扱いのぞんざいさが目につくようになり、そのうちだんだん自ら彼を探すことも減っていった。しつこいようだが、私は本当に彼が好きだった。今でもただ運が悪かっただけだと思っている。インターネットにもあまり精通しておらず、運営、公式以外から推しを摂取する方法がなかった私にとって、それはどうしようもないことだったのを分かってほしい。
彼の担当を名乗らなくなってから1年ほどだろうか。ある夜、突然目が覚めた。時計を見ると午前3時になろうかという深夜。腹痛や頭痛の体の痛みでもなく、暑さや寒さでもない。まさか霊的なものとかじゃないだろうな、と思いつつスマホを立ち上げる。ツイッターを見て、インスタを見て、2、3戦ゲームをして、とうとうすることがなくなり写真フォルダのスクリーンショットを見返していたときだった。思わずえっ、という声が出て、がばっと体は飛び起きた。
昔の推しの、誕生日だった。
ゲーム内で彼の誕生日を祝うイベントが行われていたときのスクショが、何十枚にも渡って保存されていた。それはどんなにグッズが出なくても、メインストーリーに登場しなくても、全てのキャラクターに平等に行われる生誕イベントが、当時の私にはどれほど救いだったか表していた。
頭で考える前に手が動き、私はそのゲームの公式アカウントを見に行っていた。私が何回も綴った名前と「生誕イベント」という言葉が含まれたツイートが見えた。その頃は他のキャラと比べて少なさが目立っているように見えた反応の数は今見るととんでもない数で、コメント欄には彼を今も愛すひとたちの祝い、彼が今も生きていることを感謝する言葉で溢れていた。生まれてきてくれてありがとう、来年も再来年もずっと、あなたがいるから幸せ、画面の向こうの誰かが書き込んだその文字の隙間に、確かに彼の背中を追いかけた、彼がいつか日を浴びる日をいつまでも待とうと思った自分がいた気がした。
スマホを投げ出して天井を見上げた。彼のことが本当に、本当に大好きだったな、と強く思い出した。同時に、もう私はあの人を推しと呼ぶ日は来ないだろうと確信した。だけと言わせて、誕生日おめでとうと呟いた。運営がどうだとかグッズがどうだとか、全部忘れて言ってあげたかった。今も彼はたくさんの人に愛されて今日を生きている。じゃあね、さよなら。別々の世界で幸せになろうね。かつて大好きだった私の推しへ。