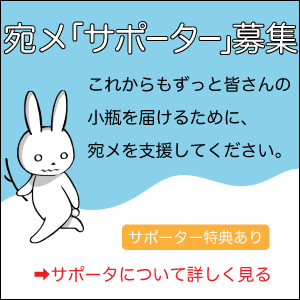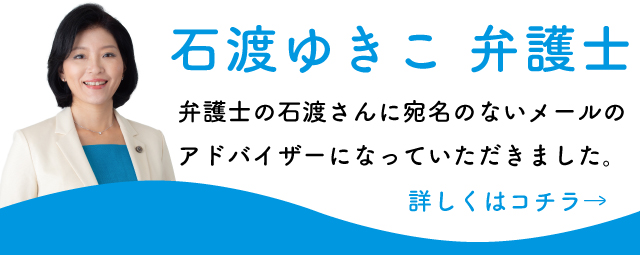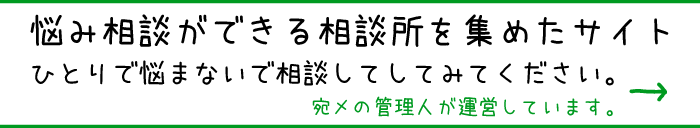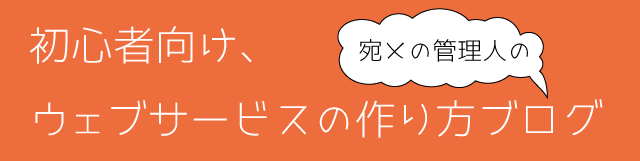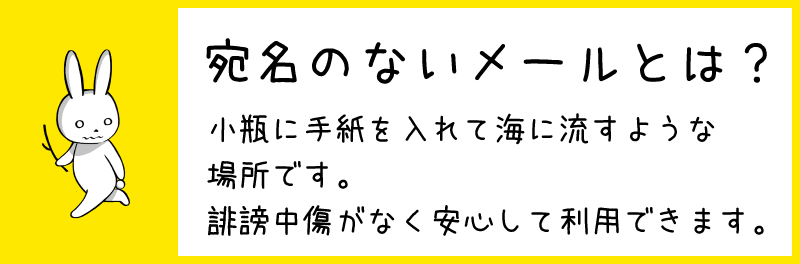

太宰治の「人間失格」
あれは究極の遺書ではないかと私は思う。
解せないのは、初めて読んだときどことなく救いめいたものを感じたことだ。
人の苦しみを消費して踏み台にして自分の生を肯定するような真似をすべきではないと思った。
少なくとも当時の私は、小説という形で世に発表されたものであろうが、そういう読み方をすべきではないと思っただろう。
幸いそこまで思い至らなかったが。
今考えれば、作者が自身を投影した主人公に、ほどほどにしか共感できなかったからなのかもしれない。
私は決して道化に徹することはできなかったし、何の分野においても天才ではなかった。
食事をすることが苦痛ではなかったし、生きるためには食事をとらねばならないという強迫観念も持ち合わせてはいなかった。
むしろ生に執着はしたくなかったのに、食事には執着していた自分が滑稽に思えた頃だった。
そういうわけで、ほどほどの共感でいられたのだと思う。
心底浸れたのは途中から入ってくる破滅願望の下りくらいだったかな。
そして滅茶苦茶な人生を振り返った主人公は、有名な一節を唱える。
「ただ、いっさいは過ぎてゆきます。自分がいままで阿鼻叫喚で生きて来たいはゆる人間の世界において、たつた一つ、真理らしく思はれたのは、それだけでした。」
ああなんだ、自分が今どれだけ滅茶苦茶な生き方をしていても後世には残らないんだ、忘れ去られるんだ。
私はそういう風に、その一節が救済であると捉えたわけだ。
どうせ忘れられるのだから、今多少見苦しく生きていたって構わないのだという救い。
期末考査が終わった昼下がり、余計な思考を追い出すために下校中歩きながらもずっと本を読んでいた中学生の私はそういう理解をした。
しかもこの作品の有名な一節はかなり最後の方にある。
残りは確か二文ほどだったと思う。
だから一度その文に酔ってしまえばまず素面に戻されることはない。
ところで太宰治は享年38だが、「人間失格」の主人公はラストシーンで27だと告げている。
これはとんでもなく突飛な妄想にはなるが、太宰治の人生における価値観は27で完成しきっていたのかもしれない。
穿った見方をすると、自分の人生は27までしか新展開がなく、残りは書くに値しないと思ったのかもしれない。
そして例の一説は、すべてが過ぎ去ってしまうのならば生きる意味はないという風にも捉えられる。
つまり、私にとって死に固執する必要はないという意味だった文は、作者にとって生に固執する必要はないという意味を持ち得る。
個人的には、冒頭の食事に対する感覚からも、作者が生に固執するべきだと思っていたように見受けられる。
そして当時の私は常々自分は死ぬべきだと思っていたので、確かに死に固執すべきだという考えだったわけだ。
ただそれは上手く生きられるのならば生きていたいという感情由来のもの。
作者はどうか。少なくとも幼少期は上手く生きられている。
傍から見れば「神様みたいないい子でした」と登場人物に語らせている。
しかしそのとき既に、当たり前に生き続ける選択をとる人々に疎外感を抱いている描写がある。
ただ悟った言葉が違う意味を持っただけ。
そうなんだったら案外、人の苦しみを消費して楽になったというわけではないのかも。
これを読んでものすごく陰鬱な気分になったという人と、逆に晴れやかな気分になったという人の差はそこで生じてるのかな。
私は後者で、これを名作だと思っているけれども、誰彼構わず勧めるべきではなさそうだ。
綺麗に生きられないから死にたい、自分は死ぬべきだと思っている人は一度読んでみてほしい。もしかしたらほんの少しだけ救われるかもしれない。
一般的に見て真っ当な生き方ができているのになんだか生きる意味が分からないという人は絶望し得るので、読むかどうかよく考えてから決めてほしい。
あのとき、家に着く前に道端でこれを読み終えた私はとても清々しい気分になった。
ちょうど4年前の今頃だ。
季節が巡り、山の紅葉が終わって風が冷たくなるたびに、何となくあの晴れやかな気持ちを思い出す。
というわけで書き起こしてみました。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。

誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項

ななしさん
この小瓶をを拾って良かったです
活字が苦手で避けてきたのですが、今度手に取ってみようと思います
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項