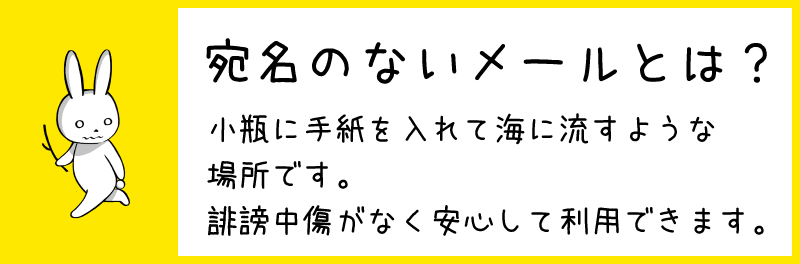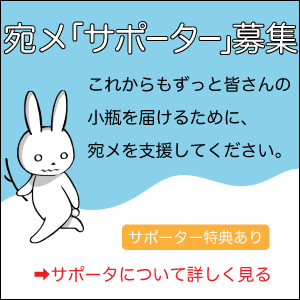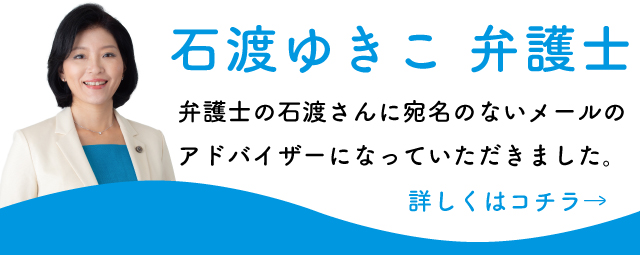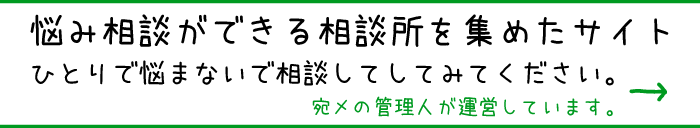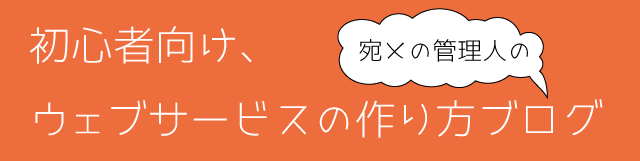ミレは普通の女子高生。学校では目立たない存在で、友達も少なく、日々を穏やかに過ごしていた。とりあえず、頭はいい方で勉強にはあまり苦労していない方だった。でも、とても苦手な教科である物理は、いつになってもミレを苦しめるものだった。
「あー今日も物理1限か」
ミレにとっては最悪な始まり方。これだとなにもやる気が起きないまま1日が終わってしまう。そんなことを思いながら、今日という日の初めを告げるチャイムが鳴った。
「えー、こういう形式の問題、よく大学入試だのなんだのに出てくるからしっかり解けるようにしとくことねー。わかったー?」
先生が言う。
「え、待ってそれ一番苦手なんだけど」
「わかるわー、よくわかんないよね、こんがらがっちゃう。大学ってこういうの好きだよねー」
ミレは隣の席のアカネと少し話していた。ミレの数少ない友達の中で親友とも言える唯一の頼り合える仲だった。そんなことを話していたらもうあと5分で授業が終わる。今日も何も理解できなかったな、と反省はしているものの、全く改善されない。どうしようと焦るも、意味ないことはわかっているからミレは「物理は捨てた」と毎回定期テストで言っていた。
今日は午前授業。ミレは帰る時、1人を好むから終礼が終わったらさっさと帰ってしまう。でも今日は数学選抜のテストがあって、なかなか帰れなかった。
「はい、解答やめ」
試験が終わった。毎回、8割程度は取れる。でもやっぱり公式をしっかり覚えているか怪しいところは怪しい。今日も帰ってから復習しようかな。
「明日の朝礼で返すから、待っててね」
定期試験の数学の点数がいい人順に並べて各クラス上位3人が選ばれる。ミレは3人中2位の成績。一位は…知らない人だった。
「ミレ、だっけ、名前」
「え、まぁそうだけど、どうしたの?」
選抜1位の人がなんか話しかけてきた!
「物理苦手って後ろで言ってたの、聞こえたんだよね。よかったら教えようか?」
え、まじか。と一瞬引いたミレだったが、この機会はいいチャンスだと思った。
「ぜひお願いしたいです」
「あは、敬語じゃなくてもいいのに」
ミレは心の中で「なんやろなーこれ。急に人が優しくなるの。最近よくある、ほんとにおかしい」と思った。そんなことはさておき、とりあえず教えてもらった。
「ありがとう、助かったよー。てか説明すごくわかりやすかった!」
「ほんと?嬉しいなぁ」
「じゃあ、私はこれで」
「じゃあね」
イヤホンをつけて音楽を流し、路地を歩く。冬だから空が高い。澄んでいて綺麗な青色をしていた。
しばらく歩くと、フェンスに何かを叩きつけるような音が聞こえた。イヤホンして音楽聞いているのに聞こえるなんて…と思ってイヤホンを外してみると学ランの人と酔っ払った人…?が殴り合ってるんだか喧嘩してるんだか…わからない。2人のうちフェンスに人を押し付けている方の学ランの男子高校生っぽい人は無表情で相手の目を見つめている。それに怯えているのかわからないけどもう1人の方は手も足も出ないような体の固まり方をしていた。ミレは恐怖心と好奇心でどうしたらいいのかわからず、突っ立っていた。すると、学ランの左の眼が赤い男子高校生がハッとした顔でこちらを見た。そして駆け足で去っていった。こっち見た、とミレは思ったが、いやそんなことないと思った。
それから二週間。毎日登下校中に必ず見かける。普通に通っている時もあれば、前みたいに暴走している時もあれば…。ちょっと面白くなって、話しかけることにしてみた。
「ねぇ、あなた大人しいじゃない。なんで一番最初に見かけた時はあんなだったの?」
「…」
「…?」
「…ほっといてくれ」
「えー」
拒絶された。話しかけ方が悪かったのかな。確かに前はこっち見てから駆け足で去ってったもんね。
「…なんかよくわからないけど、感情が高ぶると前みたいになるんだ。通常状態では全く持ってわからないものが急に考えれるようになるんだよ、なんつーの、戦闘能力?が上がる」
話してくれた。これもそうか…?私に優しくしてくれた。
「…うん」
「たまぁにおかしいのもあって、物が動いてる時もあるんだよ」
「ん?」
「物が動くの。」
「ほぉ。」
「絶対理解してへんやん」
「だってわからないんだもの」
「しょうがないか」
なんか諦められてしまった。でもそうだよね。失礼だけど友達はいないように見えるし、しかも自分から拒否している。それなら相手に自分が持っている「力のこと」なんぞ、話そうとするわけがない。それこそ私には何の力が働いているんだろう。
「ちょっと場所変えようぜ、座れるところにしよう?」
そしてミレたちは近くの公園に向かった。
「僕が情緒不安定だってのもあってさ、いつ感情が高ぶるのか予測ができなくて。たまに教室内で暴れ回った事だってあったしね」
「教室内は大変そう…。家は?」
「家…ね。なるべく家に居ないようにした」
そんなに酷かったんだ。辛そう。完全に理解できるものではないけど、わかる。
「あ、というかお互い自己紹介してなかったよね」
「あ、そうね」
ミレたちは互いに自己紹介を交わし、相手の学ランを着た学生はソラという名前だった。
ソラはミレに能力が発動してしまう時の制御の仕方を教えようとする。ただ、ミレは何のことかよくわかっていない。なぜなら自分の能力を分かってないから。そのうちソラは度々暴走しかけるが、ミレが頑張って止めに入る。それと、よくわからないミレの「能力」が働いて、また優しくなってくれる。ミレはなんで?と毎回困惑しながらも、2人で支え合いながら、能力のことを順に学んでいく。
「ミレ、お前、さ、人の感情とか動作とかを操る能力、持ってんじゃない?」
「どういうこと?」
「だってさ、もし僕がなにも能力を持ってないミレに話しかけられてもこんなふうにして能力のことを話し合うなんてしないよ。だから僕に『話して欲しい』って思って、その能力が働いたんじゃないのかな」
戸惑いを隠しきれず、ミレはおぉ…と感情を漏らした。というか、その能力のことを知ったところで、私の何になるんだろうと思った。
「まぁ、いいや。それでも自分が本当に思っていることとは別に能力が働きかけることもあるんじゃないかな、よくわからないけど。これはただ僕が推測した話だよ」
時計を見たら25:00。え、もうそんな時間?とミレは思った。
「うーん、よく理解できない!もう寝る!明日考える!」
といってミレは事前に持ってきておいた薄い紫色のマフラーを巻いてさっさと帰ってしまった。
「ふん、可愛いとこあんじゃねぇか」
ソラが吐息に近い声で言った。
家に帰ったのはいいものの、今日ソラが言っていた「能力」の事が理解できない。10分、20分、30分…刻々と過ぎ去る時間。突然ミレはいいことを思いついた。
「明日お母さんにやってみよう」
ちょっとお母さん可哀想だけど、使わせてね。
次の日。ミレが起きたらお母さんが朝食を作っていた。
「おはよう、あら、クマすごいわね。何時に寝たの」
「ん?いつも通りだよ」
「ならいいわ」
今日は学校がある。でもソラに会いたい。話がしたい。「理解できたよ」って言いたい。んじゃ、幻覚、視せるよ。ミレは早速ミレのお母さんに「能力」を使ってみた。
「あら、今日は行くのが早いのね」
おお、効果的中。よしっ、と思ったミレはそっと玄関の鍵を開け、昨日ソラと話した公園に向かった。
「おはよう、ソラ」
「…お、来た。早いな」
ミレはソラの言ったことを無視して言った。
「私理解できたよ!」
「声でか…」
「あ、ごめん」
周囲の人がチラチラこちらをみている。気まずい。気まずすぎる。
「まぁよかったな。それじゃあ、前言った制御の仕方で制御してみて。実際に聞くかどうかはわからないけど。」
感謝してもしきれない。そして、少し世間話をしていた。すると後ろから聞き覚えのある声がした。
「ミレ、何でこんなところに…」
「おかあ、さん…?」
ーーーーーー
前編終わり
本当に話の流れ早すぎて困るでしょ
後半はもっと速いんだよね
そこらへん修正しながら明日後編出します