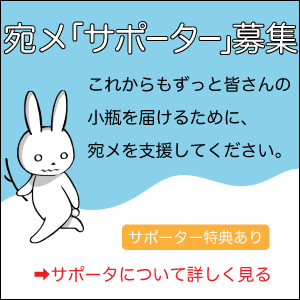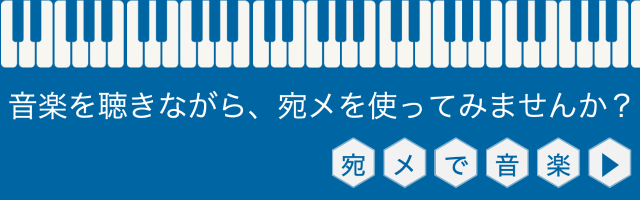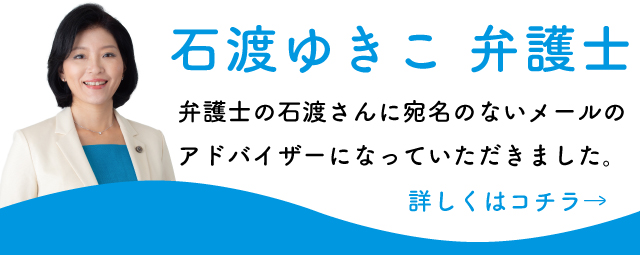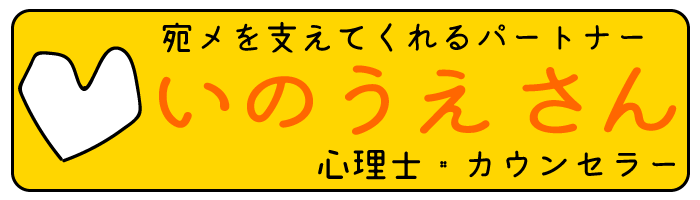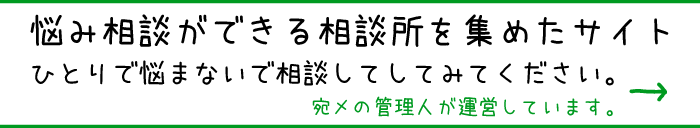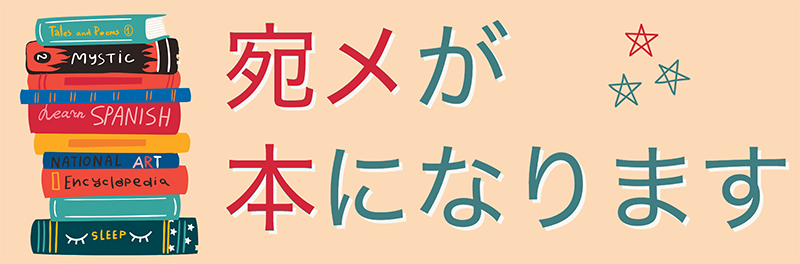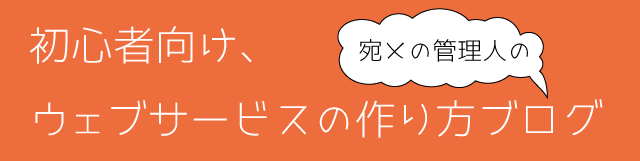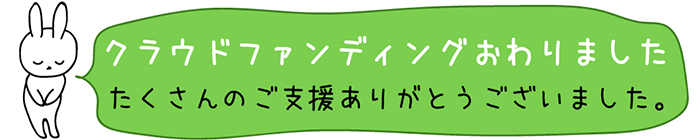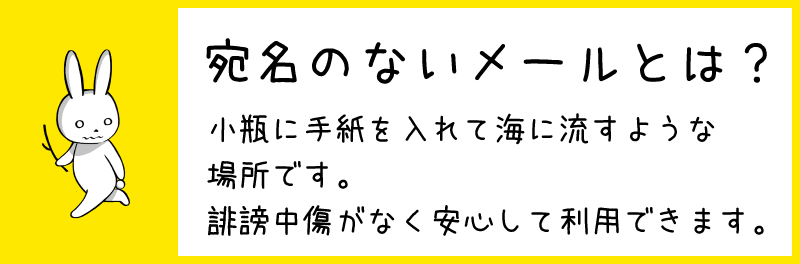
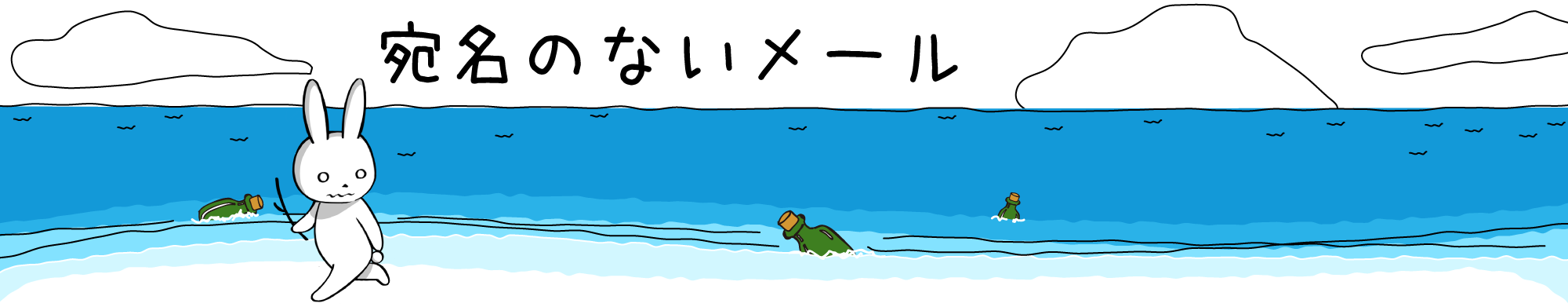
以前から疑問に思っていることがあります。
震災や自然災害によって起こった事故などを忘れてはいけないという言葉をよく耳にしますが、いったいそれがどのようなことなのかどのような意味があるのかがさっぱりわかりません。人々の記憶に残しておく必要とはなんですか?
記録があるのなら覚えておく必要はないのではないかと私は思ったのですが。
戦争を忘れてはいけないということは、戦争をすることに対しての抑止力になりますが、技術者でない一般的な国民が自然災害によって起こった事故を覚えていることだけでなにかが変わるとは思えないです。
忘れてはいけない、忘れないでほしいと思う気持ちが理解できる方、僕にどういうことなのか教えていただけませんか?
よろしくお願いします。

誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項
一通目さんが言われてるように、そういう事があるんだよ、という意識があればこそ、対処しようとも思える、という事かもね。
津波や地震の知識がなくて、逃げる時に逃げませんとか、何が起こったかわからずパニックになって、机の下に隠れたり自分の身を守れませんでしたでは、済まされないというか、なんか悲しくない?
俺は虚しいというか、悲しい。
どんな事が実際あったのか実感を持って生きる人も年を重ねれば減ってくし、そういう意味で新しい世代が知識を継いでいくのも、大事な事だと思う。
戦争を忘れてはいけないのは、抑止力のためというか、それだけじゃなく、国を守る為どれだけの命が散って行ったかという事でもあるし、残された人がどんな思いをして行ったかという事でもあると思う。
嫌な話をすると、戦争の悲惨さ…、例えば、戦争の為に軍の補給地を叩く戦法といえばわかるかな。
つまり、国自体、非戦闘員としての国民が戦火に包まれる可能性はあるんよ。
兵士として出て行った人にも、家庭や人との繋がりはあるし、その悲しみだってある。
よくテレビで取り上げられてるような気もするけど、災害にもそういう面はあるよね。
あと、震災いじめみたいな意味のわからんもので、被災して家がなくなったり、家族との繋がりが断たれたりされた方々を更に傷付けるような出来事もあったようだし。
そういう心の問題としての、忘れて欲しくない、そんな思いして欲しくない、というような事もあるかもしれない。
ぶっちゃけ、技術者じゃなくても、災害によって割れて散らばったガラスの破片から足を守る方法や、ガスの元栓や電気のブレーカーを落として、火災などの二次災害を防いだりと、身を守る方法はある。
災害があるという記憶から、防災意識も芽生えるものだろうし、いざという時に食料がなくなっても困るから、乾パンだとかの非常食もあるだろう。
起きてからじゃ遅かった、カバーするのが大変だった、というような大きな出来事があったという事ではないかな。
いざという時に身の守り方がわかっていれば、守れる命もあるだろうし。
一般人としては関係ないかもしれないが、場合によっては、技術者になるような人も出てくるかもしれない。
変わるのは、まず認識として、災害があるという意識。それから、それに対処出来ないかという意識。
そして、それらが行動に繋がるんじゃないかな。
覚えているだけでは確かに、何かが大きく変わる訳ではないかもしれない。
でも、一人一人が覚えている、というのは、一人一人の行動が変わる為の架け橋にもなると思う。
まあ、記録だけじゃなく、一人一人が災害の中に放り出される事がある訳だし、そんな時に電気やら紙媒体やらの記憶が頼りになるかっていうと…ねえ?
電気も止まるかもしれないし、紙だってぐちゃぐちゃになったり、引き出しが開かなかったり、家自体が潰れたり、流されるかもしれない。
正直、俺には、人の記憶だって確かなものとは言えないけれど、身に付けたものは、役に立つと思う。

ななしさん
ちゃんと頭に入れて、防災や対処ができるようにしろという話なのでは?
起こってから記録を漁るのでは遅いですし。
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項