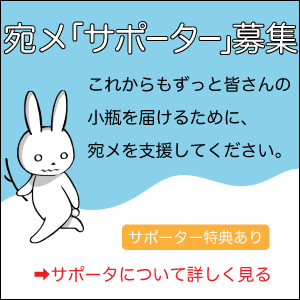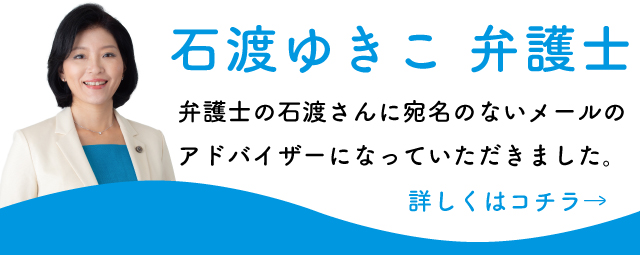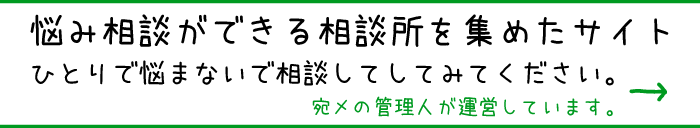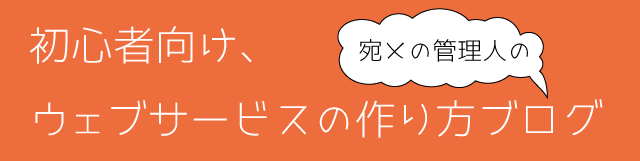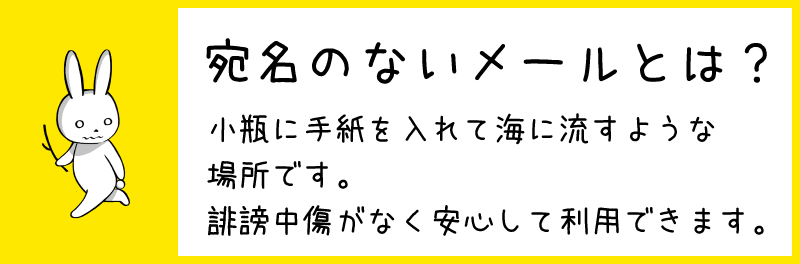

ずっと前のある時期、空想するのが癖になっていた自分は、ある物語を思い描いていた。
物語の主人公と、主人公と一緒に行動する不思議な雰囲気の少年。舞台は、まだ都会に出たことがなかった頃に想像した、輝く夜の繁華街。
今になって、その都会のイメージはおおよそ合っていたことを知った。
しかし、街の暗い路地裏をどんなに探しても、その少年はいない。
コンクリートの壁に寄りかかって、主人公と喧嘩したり、腹を割って自分の話をしてみたり、今思えばあまりにも稚拙な目的を、恥ずかしげもなく堂々と言ってみせる。
どういうわけか、街は埃なのか排気ガスなのか分からない架空の臭いと関連付けられて、その臭いを忘れてしまった自分はもうあの物語を進められなくなった。
感覚が大人になったのかもしれない。
しかし、あの物語に出てくる台詞は、中学生の頃の感覚をそのまま体現している。
それを、大学生になった自分が否定するわけにもいかず、未だに物語の落書きノートも残してある。
いつかは捨てられるだろうとは思いながら。

誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項

ななしさん
それがあなたの重みになるのなら捨ててもいい。でも、もう少し待ってもいいのではと思う。いつか路地裏からひょっこり現れた少年にその落書きノートを渡すかもしれない。
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項