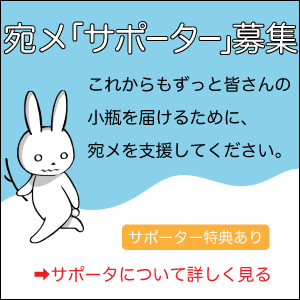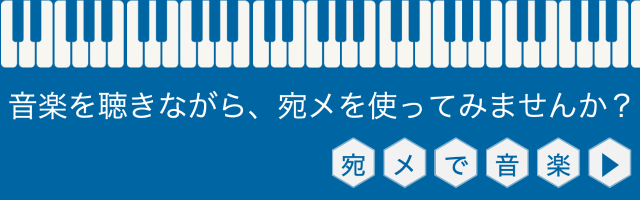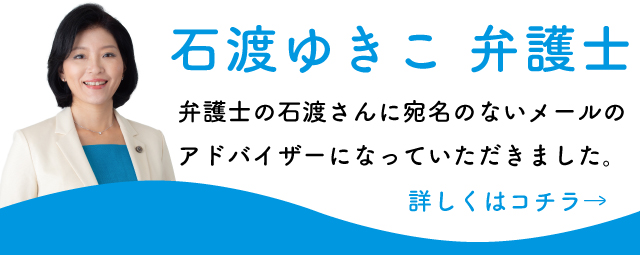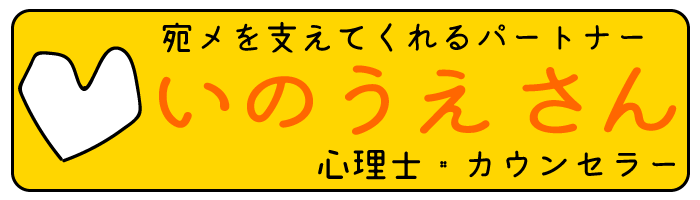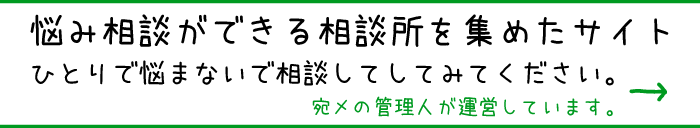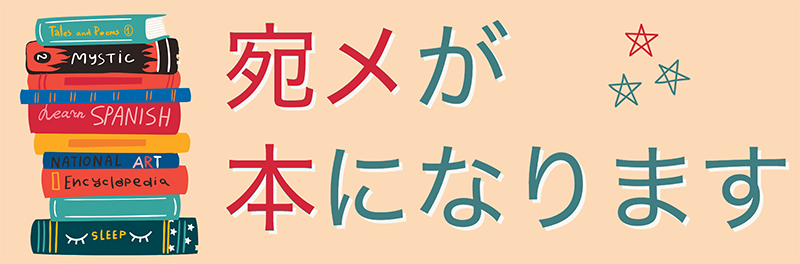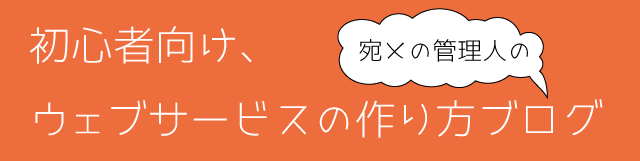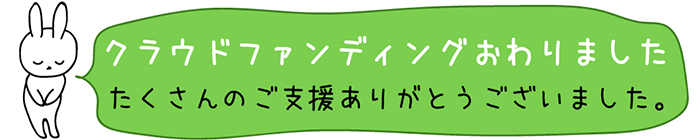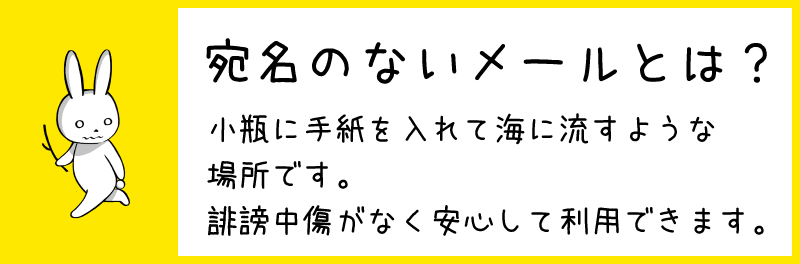
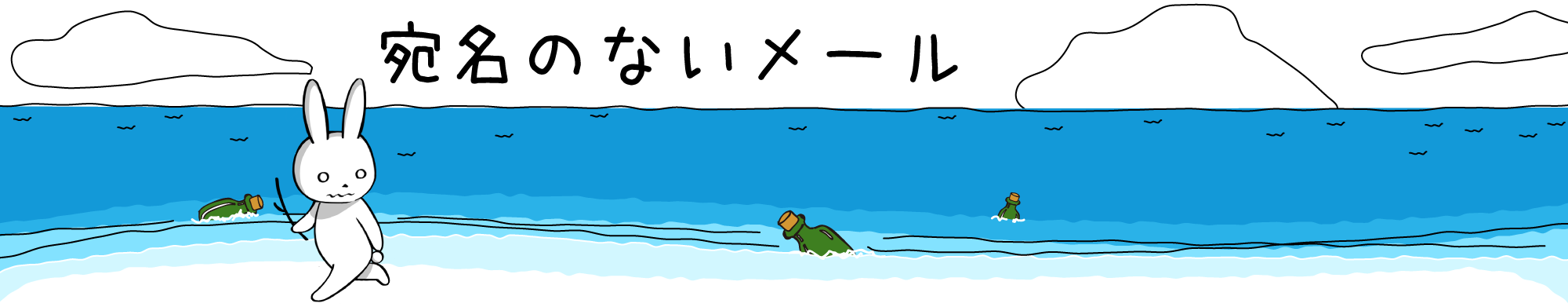
簡単な問いほど、誰も答えられないんだ。
当たり前だと思ってることほど、それを質問すると「本気で言ってる?」とか「なんとなく分からないかなぁ?」とか返ってくる。言語化できないんだ。
先日、母に質問したところ「本気で言ってる?」と言われて軽蔑しそうになりました。
「赤信号を渡ってはいけないよ」
「どうして?」
「危ないからだよ」
「どうして危ないとダメなの?」
「死んでしまうかもしれないからだよ」
「どうして死んでしまってはいけないの?」
「みんな悲しむからだよ」
「どうしてみんなが悲しむとダメなの?」
「……本気で言ってる?」
思いついた例です、ひとりで考えてるから不自然なところもあるかも。ソクラテスですね。
でも自分は無知の知とかいうことに興味はなく、ただすべてが分からないだけなのです。善悪が分からないだけなのです。
辞書なんかじゃこの世を定義できはしないので、自分が定義づけするしかないのですが、これがなかなかどうして難しい。
でも定義づけしないと気持ち悪い。自分の希死念慮のいくらかは、ここからきている気がします。
さて、どうしたものか。
余談ですが、自分は悲しいという感情がどうしても分からないのです。
感情はあります、怒りも感じます。喜び……は最近感じないけど、昔はよく喜んでました。
でも「悲しい」は難解です、分からない。
何か感情に泣かされたことが怒ったとき以外に思い当たらないのです。悲しいってなんですか。

誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項
東京大学医学部で解剖医をされていた養老孟司さんは、自身の死についてこう語られています。
「自分が死んでも、自分は困らない。周りは大変困るでしょうが。」
それとは別に明治時代の死生観についても講演で話されています。
以下は講演内容を一部抜粋したものです。
『明治の頃、幼児死亡率が非常に高かった。
3歳、5歳の可愛い盛りの時に死なれた親の気持ち、多くの人が知ってたんです。
子供が死ぬ社会では、親は死なれた子供のことをなんとなく思い出しませんか?
そのくらいの歳の子が遊んでいると、うちの子も生きていたらあんなかと。
それと一緒に必ず思うのが、「あの子の人生、一体なんだったのだろう。」
3歳なり5歳で死んでしまう。
そうすると今、遊んでいるあの子は人生で非常に大きな時期かもしれない。
その人生を思う存分生きさせてやりたいと思うのが親の気持ち、大人の気持ちだと思います。』
恐らく小瓶主さんは「死」とは「自分の死」として、捉えているのかと。
自分と関係が深い人の死は、体験しないとなかなかわからないものでして。
私も自分には心がないのかと思うほど、世間と自分を分けて考えていました。
しかし、兄の死は別でした。
唯一と言っていいほど近くにいたもので。
これが涙が溢れる、
これが悲しさなのかと。
求められる回答ではなかったかも知れませんが、私はそのように思います。
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項