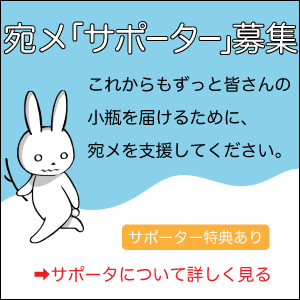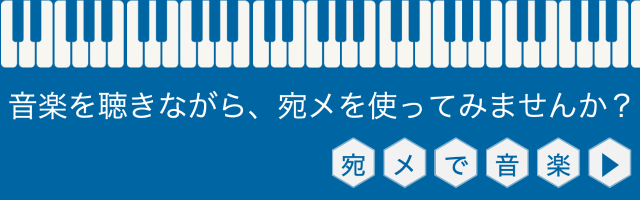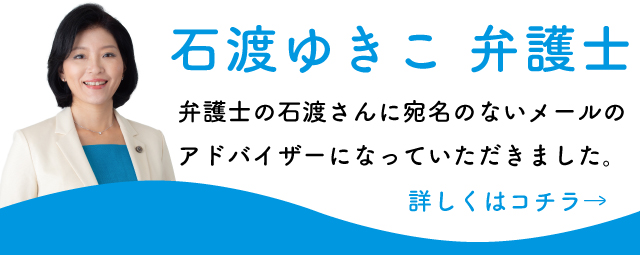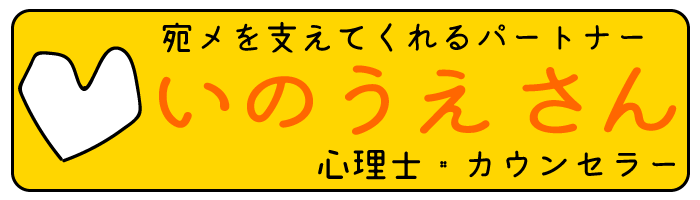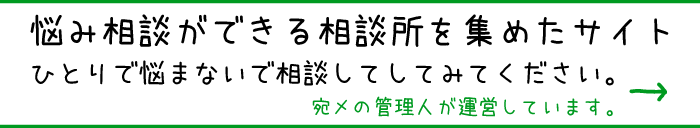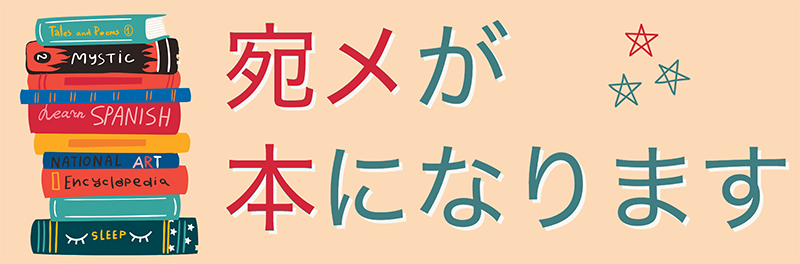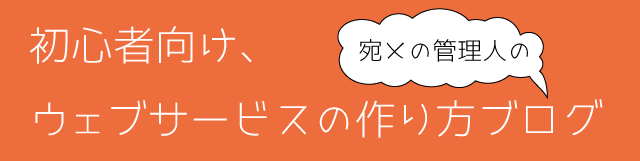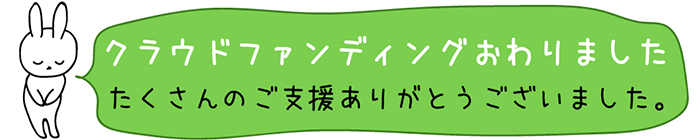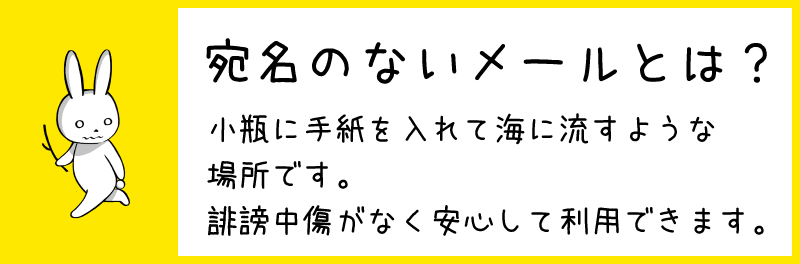
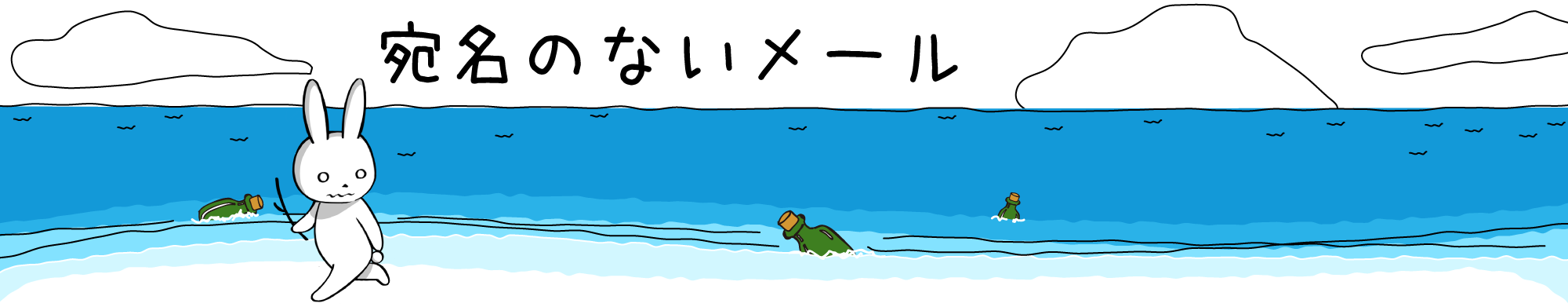
以前、「仮想敵を生産するくせがあり、そのせいでしんどくなる」という小瓶を流したことがある。
仮想敵というのは、自分がやることなすこと全てにケチをつける存在のこと。頭の中のもので、実体がないぶん自分は貶されっぱなしだ。いや、論破するにはするのだが、論破したところで仮想敵が与えてくるダメージが消えるわけではなく、それはただ蓄積されるのみだ。
そのとき、お返事で
「それだけ仮想敵を作るのが上手いなら仮想味方を作ればいいじゃない」
と言われたが、それとこれとは全く別物なのだ。
これは「仮想」じゃなくても言えることだが、敵と味方は全く別の捉え方になる。
ここで、敵を自分へのアンチ、つまり、自分を貶してくる存在、自分を阻むものとし、
味方を敵の逆、つまり、自分を擁護してくれる存在、自分の背中を押すものとする。
この世界には「敵でも味方でもない人物」が少なからず存在するが、今回それは無視して構わないだろう。
自分は、敵より味方のほうが信じられる、と考える。
信じられる、というのは、「信じるに値する」ではなく、「信じることが出来る」という意味だ。
このジレンマは、自分の防衛本能に由来する。
敵を敵と信じても、自分に不利益はそんなにない。
たとえそれが味方であっても、相手が「そう見えるように振舞った」点においてそれを信じたことは責められるべきではないからだ。
認識の相違で敵対した場合、後でそれが発覚すれば改めれば良し、発覚しないのならその事実はなかったことと同じだろう。
認識の相違により敵対していた相手が無二の友になる可能性だが、それを言いだすと全ての人間関係を切れず、人生において重荷になるので無視したい。
対して、味方を味方と信じた可能性だ。
確かに、味方を味方と信じることに対するメリットは少なくない。
だがそれは同時に、大きなデメリットも秘めているのだ。
「味方が敵だった場合」のデメリットは実に容易に想像がつくだろう、それはつまり「裏切りによるショック」だ。
とても身近な例でいえば、「自分を親友と呼んでくれた相手が自分の知らないところで陰口を言っていた」ことだ。
自分は経験があるし、それを経験したひとも少なくないと思う。自分の知り合いにもいる。
まとめると、
「敵を敵と信じる」ことはノーリスクノーリターン、
「味方を味方と信じる」ことはハイリスクハイリターンであると自分は考えている。
言語化が難しいが、ここでいう「リスク」「リターン」とは自分が一生認識しないことは含まない。
(先の「敵が無二の友となる可能性」は、例えそうだったとしても無二の友とならない限りそのことを認識しないから、ここでは「ノーリスク」と扱う)
定義づけをところどころ挟んだから、冗長だと感じられた方には申し訳ない。
しかし自分にとって定義づけは大切なのだ、「認識の相違」を起こさないために。それでも起こってしまうのが人間間のコミュニケーションではあるが。
つまるところ、自分は「仮想味方」を作ったところで支えにはならず、逆に邪推してしまって余計な気苦労が増えるだけなのだ。
「自分を追い込むほどの仮想敵を創造する想像力」というのは、そんなバカみたいな話も引き起こしてしまうのだ。
補足として、実体がない仮想敵に実体を与えることは無意味だ。どんなにキャラデザを凝ったところで、実体がない強みには敵わない。実体のない仮想敵が話すことは止められないのだ。
わざわざ手加減してくれる敵なんて、もはや敵ではないでしょう?

誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項
 つな
つな
「絶対裏切らない」という保証付きの人間なんていないので無理です
「裏切らない」と信じることは物理的に可能ですが、他人のこころを完全に見ることが出来ない以上、「裏切らない」という確信はどう足掻いても得られません
得られたとしたらそれは勘違いだし、脳内お花畑なだけです……それはそれで幸せなので羨ましいですが
唯一裏切らないと確信が持てるのはこころを共有(物理)している相手、つまり自分ですが、仮想味方や仮想敵のこころを自分と同期させてしまうとそれはもはや敵味方とは呼べず、ただの「わたし」になってしまうので無意味です
小瓶に書いた通り、わたしにはそれだけの想像力があるのです
まあ、わたしは自分の気持ちすら分からないのでそれすら信用も信頼も出来ないのですが
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項