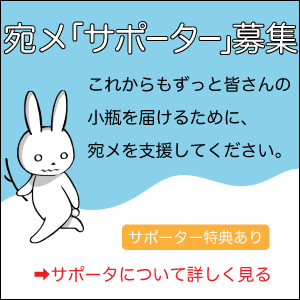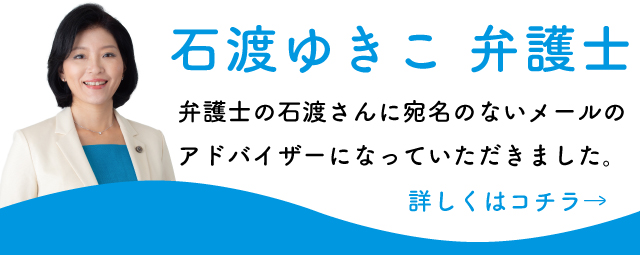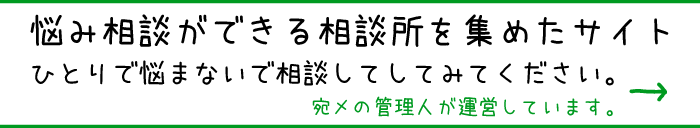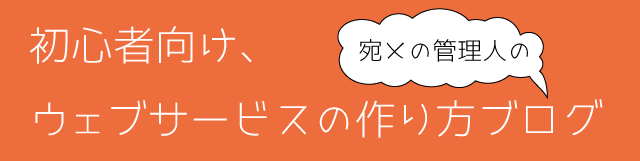突然に、強烈な光に目を奪われた。
光は、漫然と揺蕩う私に、形を与えてくださった。
感じたこともない高揚と敬愛が、確かにあった。
個となった私は光に照らされ影を生んだ。
彼らは眩しくて、眩しくて。
影は濃度を増すばかりであった。
いっそう強く光る彼らが、恨めしく思えた。
小さな光でよかった。灯火で充分だった。
だのに、彼らは星を目指していた。
星をめざし、世界を創ろうとしていた。
余計なことを。そう思った。
闇の中で小さく生きてくれていれば、それで良かった。
しかし私は、そんな彼らに惹かれたのだ。
それは恨めしく。
それは寂しく。
──不甲斐なかった。
光に目を潰された訳ではなく、しかしその光に身を焼かれる弱い私は、ここに居るべきでは無いのだろう。
彼らのパレードに私は最早追いつけなくなってしまった。
ずっと昔に察していた。とうに理解していた。
しかし私にとって光は全てなのだ。
無為に漂う私に形を与えてくださった。
生んだ影と同じほど、救われてきた。
光を知らなければと、思う日もある。
しかしそれ自体に後悔は一切無い。
例え何度過去に戻ろうと、その生で私は光を目指すのだろう。覚えていなくとも、あの光は否が応でも目に入ってくるはずだ。
これは敬愛で。依存で。崇拝だ。
今更闇に戻る勇気など、持ち合わせては居なかった。

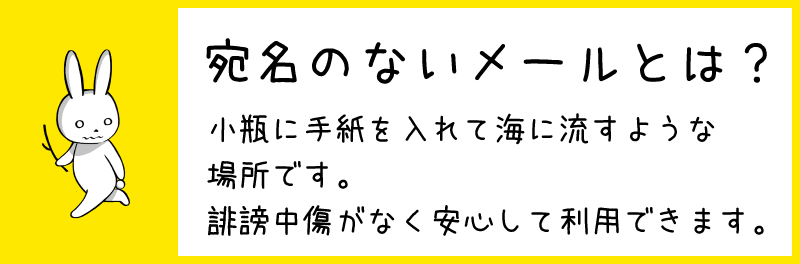


 mzk
mzk
 AAAA
AAAA