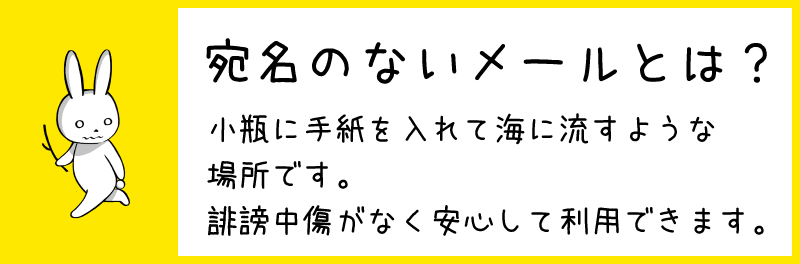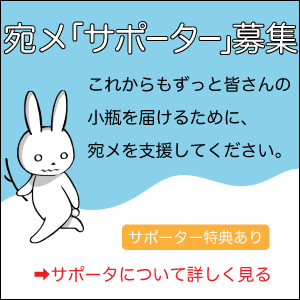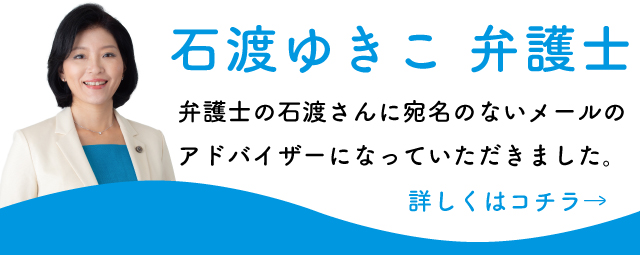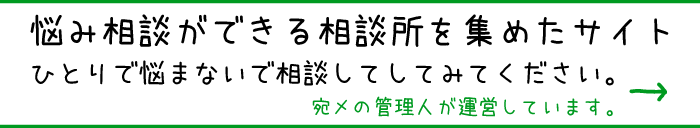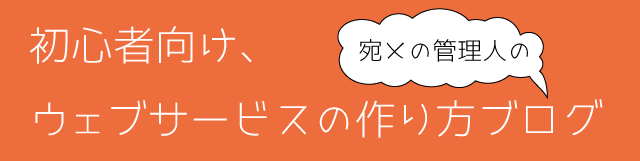中々に長いので時間がある時にでも読んでくれたら嬉しいです。
これは彼についての私の記録。
今日は高1までの話だけ書いて寝ます。
私には大切な人がいる。
友達、部活の仲間、元クラスメイト、同郷の友、親友、理解者、対話相手…
彼と私の関係を表すには、どの言葉も合っているようで違う。
だから、ある時から彼が使っている言葉、"家族"という表現が1番的確なのだと思う。
もちろん血は繋がっていない。
でも心はほんとうの家族よりも繋がっている気がしている。
言うなればきっと双子の片割れのようなもの。
どちらが上でもない、対等。
彼とは中学が同じで、でも当時はそんなに仲良くなかった。
高校で同じクラス、同じ弓道部に入っても、彼はしばらくはただのクラスメイトに過ぎなかった。
初夏のある日、宇宙の話をして仲良くなった。
ブラックホールの中はどうなっているのかとか、いつか宇宙が無くなったらどうなるのかとか、そんな話。
ロケットが好きだという彼は、こんなに真剣にこの話したの初めてだ、って言って、初めて見るような笑顔を見せてくれた。
部活で彼が怪我をした時、人間らしいと思った。
いつも飄々としていて、1年生の誰より弓道が上手いから、心のどこかで機械みたいだと思っていたのかもしれない。
彼に親しみが湧いた。
11月ごろ、どういうきっかけだったかはよく覚えてないけど、彼の話を聞いた。
彼は同級生の部員(Aちゃんとする)と仲良くなって、色んな話をして、お互いに心を許していた。
Aちゃんからの提案で、2人は付き合うことになった。
2人は仲良くなりすぎた。
近付きすぎて、Aちゃんは、我儘も、彼の嫌なところまで、何でも言うようになってしまった。
終いにはAちゃんは同じ部活の他の男の子(Bくん)を好きになって彼と別れた。
Bくんともすごく仲が良かった彼は、Aちゃんとの関係に悩んで、苦しんで、怒りも溜まって、部員のCちゃんに全部相談した。
でも、それが良くなかった。
Cちゃんは、ある時、その内容を悪気なくAちゃんにそのまま伝えてしまった。
それを聞いたAちゃんはひどく怒って、彼により冷たく当たるようになった。
信じていたはずのCちゃんに(意図的にではないとしても)裏切られた痛み、それは私には到底想像がつかないほど苦しいんだろうと思う。
彼は、部活に行きたくない、もう辞めたいと何度も繰り返していた。
でも、弓道は誰より大好きだった。
だから、学校の弓道場を使える権利、大会に出る権利を捨てたくはなかった。
部活が終わった後の暗くて冷える夜に、よく駐輪場まで2人で歩いて、立ち止まって何十分も話をした。
私にはその時間が心地よかった。
彼はよく、「沈みたい」と言っていた。
死にたい。自分の存在を消したい。最初からいなかったことにしたい。海の、マグマの、1番深いところまで沈んでいって、そのまま溶けて消えてしまえたらいいのに、と。
死なないでほしいと何度も伝えた日もあった。
けど、彼の言葉に同調する日も多かった。
また、その頃の私は、自分をどうしようもなく醜いと思っていた。
恋人と別れてから半年も経つのにまだ囚われたままの自分と、別の学校で部活やバイトや趣味や色んなことで充実した日々を送っている相手。
また、そんな元恋人からのLINEの通知一つで喜んだり憂鬱になったりする自分がどうしようもなく愚かだった。
冷たい態度を取られた回数だって数えられない。それでも「好き」を捨てられなかった。
そんな話を、よく彼にもした。
時々相槌を打ちながら、彼は静かに私の話を聞いていた。
1月の終わり頃、彼は学校を休んだ。
大丈夫?とLINEで聞いたら、親戚の医者曰く、鬱になってるらしい、と返ってきた。
その日からしばらく彼は教室に来なかった。
いつからか、美術の授業がある日は最後に教室を出て2人で話しながら教室を移動するようになっていたから、1人で歩く廊下が広くて冷たいものに感じられた。
一緒に雪を見たかった。
その後、放課後少しだけ、午後の講演会だけ…というように少しずつ教室で過ごすリハビリをした結果、1ヶ月後くらいに彼は戻ってきた。
心配するクラスメイトに「新手の不登校」ってケロッと答える彼が可笑しかった。
聞き慣れたあの声をまた毎日聞けるようになって、心から嬉しかった。
部活を辞めたいとはずっと言い続けていた。
まあ結局、3年の引退まで(一部の仮退部期間を除き)彼は部活を辞めなかったのだけれど。
顧問に色々相談しても、部長に辞めたいと言っても、お前は戦力だから辞めるなと、そういう風に止められたそうだ。
彼は、戦力としてではなく、他の誰でもない自分自身を止めてほしかったと言っていた。
冬頃から色んな話をしていく中で、私は彼に依存するようになっていった。
だけど、私自身辛い思いをしていたから、恋をするのは怖かった。
大切な人との関係をもう壊したくなかった。
また、彼もAちゃんへの想いを断ち切らずにいた。
どれだけ冷たくされても、周りの部員に自分の悪口を吹き込まれていても、どうしても嫌えなかった。
それを私はよく知っていた。
彼が自分の愚かさを嘆くたび、私はより一層自分の醜さを知った。
彼はAちゃんが好きで、私はどう頑張ったって部外者で。
話を聞いて、心を休ませてあげることしか出来なかった。
だから、彼が自分の現状をAちゃんに話したと聞いた時、ショックを受けた。
彼を分かって受け入れられるのは自分だけじゃないんだ、私は傍観者なんだと思い知らされて、授業に身が入らないほど動揺して、少しだけ泣いた。
ある時、彼に私は「止めてね」と言った。
好きになったらもっと依存してしまうから、と。
でも、遅かったんだと思う。
彼はいつしかなくてはならない存在になった。
彼が死にたいと言うたびに悲しみが大きくなった。
側で生きていてほしいと願っていた。
でも、先述した通り、彼との関係を壊すのがとてつもなく怖かった。
拒絶されたらどうしよう、上手くいかなくなったらどうしよう。
自分の失恋の痛みも恐れながら、それ以上に、好きだと伝えてもっと彼を苦しめることも恐れていた。
そこで彼の言い回し、"家族"だ。
私はその言葉で自分を抑え込んでいた。
彼への想いに蓋をして。
ひとまずひと段落。
また書きます。