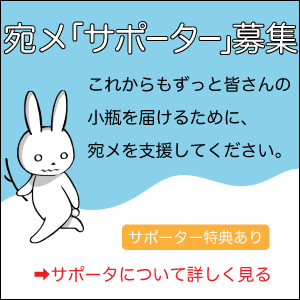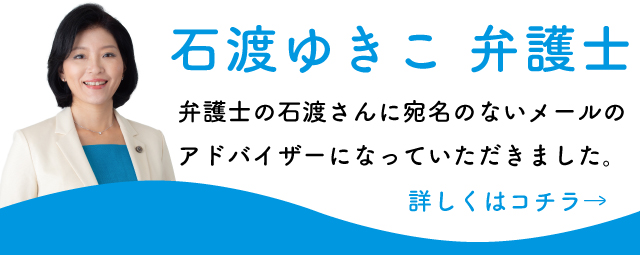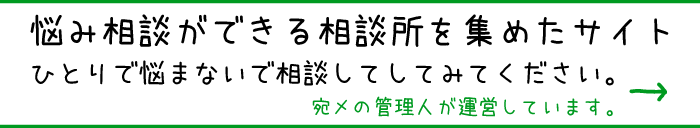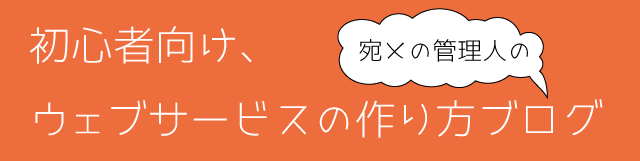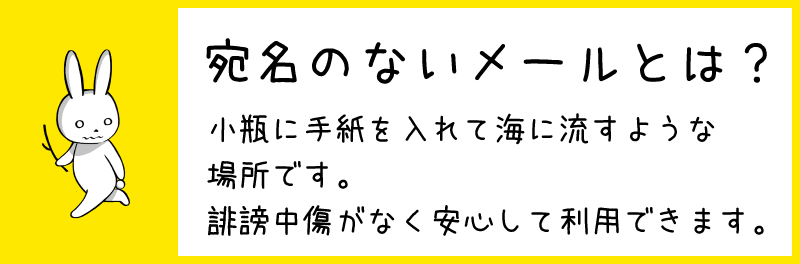

今も茨の檻の中、一人。存在の無い王子様を待っている。汚れた都会の空の下、かじかんだ手で、君の、更に冷たい指を欲している。
ねえ、私の人生に色をつけてくれた君。後輩なのに私よりもずっとずっと賢くて、鋭くて、何でもできた素敵な人。6年間も好きでした、いや、今でも好きなんだけど。
幼かった私は、毎日毎日気持ち悪くアタックして、それが愛だと思い込んでいました。馬鹿で迷惑だったでしょう。それに気付いて離れて、もう一年経ったのに。君は何食わぬ顔で夢に出てくるのですね。狐みたいに笑って、あの日の様に私を転がすのですね。
ずるいなぁ。諦めきれないのは、君がずるいからだ。興味ないなら切ってくれればいいのに、「貴方次第ですよ」と、どこにも繋がっていない赤い糸を小指に巻いたのは君なのだ。何故、私の言葉を拒まず嚥下したのですか。そして、何故、返答を曖昧に濁して飼い慣らしたのですか。私は従順だったけれど、でもそれだけで、なんのお役にも立ちはしなかったでしょうに。
離れたら追いかけて来る筈も無く。このまま別々の道を進むのでしょう。君にとって私、一体なんだったのかしら?いなくても構わないペットだったのなら、最初から餓死させればよかったのに。衰弱したまま生き長らえるのは辛いもの。飼い主の君にはわからないだろうけれど。
私の人生に色をつけてくれた君。この先未来ずっと永遠、誰も上から塗り潰せない真っ黒な絵の具で、私のキャンバスをぐっちゃぐちゃに塗りたくって。許して欲しければ、私を殺して下さい。
いっそ。

誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項

ななしさん
ポエムの才能ありますね
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項