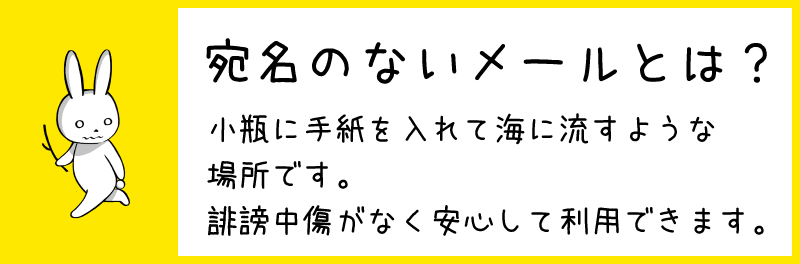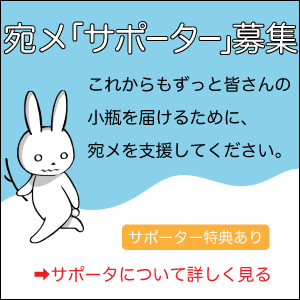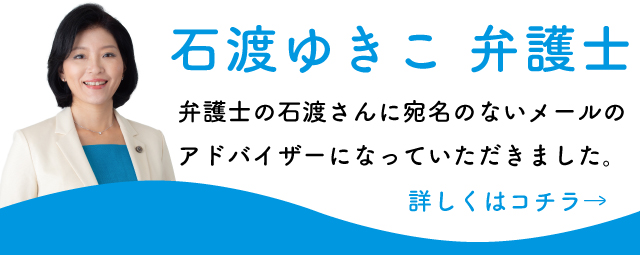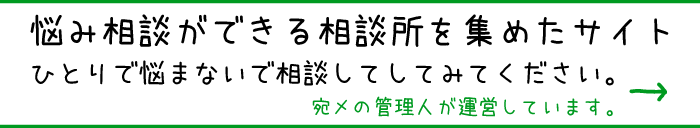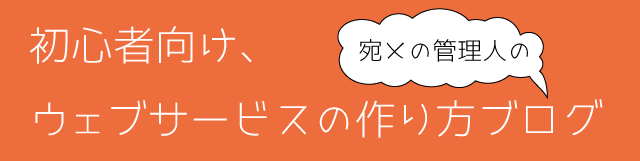烏羽
烏羽
赤い月。
青い月。
いつも人など知らんぷり。
だけど人には顔向ける。
月は何をみてるのか。
地球か、自分の距離か。
それはだれにもわからない。
きっと月にもわからない。
人にはわかるかもしれない。
けれど、それは月の思いではないかもしれない。
月は人間じゃないもの。
人は月にはなれないもの。
人は人、月は月だもの。
月も人も、過去にはなれないもの。
闇と光に溶け込んだのは、太陽の光でしかないもの。
月に映り込んだのも、星の光でしかないもの。
それも、地球の風を合わせれば、地上から人が見たものでしかないんだもの…。
昔の人だって、わかっているさ。
どうしようもない思いが、写り込んでしまうものなのさ。
地球はなにで出来ている。
月はなにで出来ている。
太陽はなにで出来ている。
人はなにで出来ている。
いくら賢くなったって、いくら体が大きくなったって。
地球も月も、太陽も人も、みんな自分がなにで出来ているのかなんて、しりゃあしない。
わかる筈もない。
土に聞いても、水に聞いても、誰もいない空間に呼びかけても、そいつらも自分が何で出来てるかなんて知らない。
教えてなんかくれない。
それでも。
それでも、その時その時考えて、回って回って、疲れたら休んだらもして。
そうやって日の光や、月の形や、地球のありようや、人の行く末がある。
今や命が欲しくて生きてるのか。
命を得たから生まれたのか。
それもこれも、誰も知らない。
それでも光の当たるところへ。
暗がりのあるところへ。
そのバランスに疲れれば、目を閉じて眠る。
なぜ繰り返すのか。
なんのために繰り返すのか。
そんなものは求めちゃいない。
日の当たるところが心地よかった。
安らかな暗がりが恋しかった。
その中の一瞬。
まやかしかもしれない、夢かもしれない。
そんなようなあやふやな、けれど確かな、確かに自分がここにいるんだと。
色んな人や、色んなものが確かに存在するんだと。
そういうものを、求めてる。
赤い月。
青い月。
ああ地球が赤いのか。
ああ地球が青いのか。
ああ太陽の光なのか。
ああ宇宙の闇なのか。
そんなものはどうだっていい。
赤い月、青い月。
それが素晴らしい。
だから言葉を尽くすのだ。
だから自分を尽くすのだ。
だから命を果たすのだ。
自分の輝きの大きさなど見えもせん。
自分の暗がり深さなど見えもせん。
その中にあって目を開けようとすれば、眩し過ぎて目は疲れ、暗過ぎて目を開けた事も忘れる。
人は星にはなれぬ。
人を照らすも烏滸がましい。
人を導くも烏滸がましい。
しかして、星だった人はいる。
星になろうとせず、人であろうとしたが星は。
月は夜を見、太陽は朝を見、星は遠くから眺めるのみ。
地球は踏み台などではなく、時に怒りを持ったように、時に慈悲を持ったように、共にある。
いかに輝こうとも、おのれの領分を超える事はできない。
人が真なる星になる事など、出来ようもない。
しかし、星の輝き、瞬きばかりが、星の存在を示すものでもない。
闇よ闇よ、音も姿もなき闇よ。
それらはずっとそこにある。
光ある限り、そこにある。
それらは決して、人を惑わせる為にあるものでもなく。
人に頼られるためにあるのでもなく。
お互いが立ち、知らず知らずの瞬きの為、そこにあるのではないか。
喜びが為でも、悲しみが為でもなく。
ならばどうしようもなき果ての悲しみはどうしたらいい。
月に問い、太陽に観てもらい、地球とともに、己の輝きを目指す。
空も海も広いなあ。
そう思わんか?
風の流れも海の流れも、どこから来てどこへ行くかはわからん。
だが、長い時を経て、ゆっくり巡り巡るものでもある。
さて…。
海流の流れや、プレートの流れは、変わるのかね。
山があれば風がぶつかる。
風が湿っていれば雨が降る。
湿ってなければ旅に出る。
持つ風持たざる風。
土は何を心地よく思うのか。
だが、風は待つ事はできん。
湿り気を帯びるその時を、待つ事はできん。
人は…、人の身には、ようわからんなあ。
誰ぞの事情はわからんが、そう思うよ。
いつか…、思い返せば、ずっと前もそんな事を思って、何か書いていたような気もするんだけどね。
まあ、現在の連続の先に、今があるわけだしさあ。