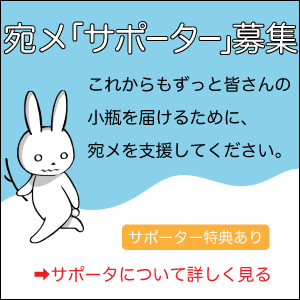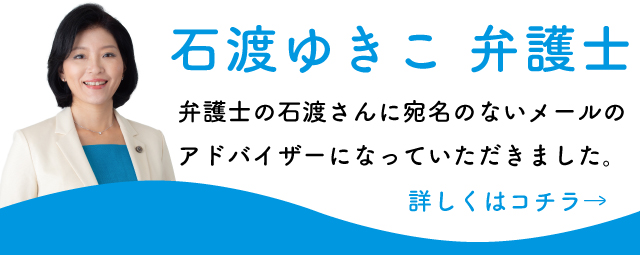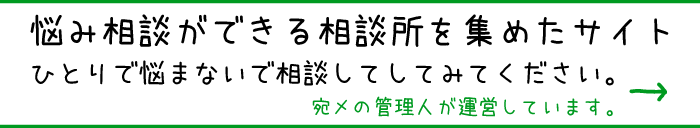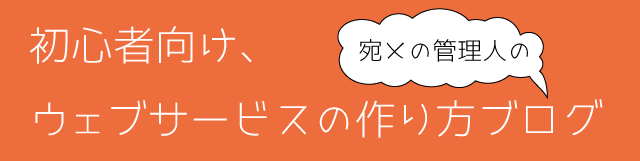夏のむせ返るような暑さの夕暮れ。雪の住処が懐かしくなり、寝台列車に乗った。人がこれから行くはずのない方へ。
切符に穴を開けてもらった。駅のやや狭いホームから見える殺風景は、夏と冬の違いすら、見ただけでは分からない。列車に入ると、昼間の熱を帯び、湿気と未だに差してくる反射光がそれをより強く感じさせた。多量の汗が空中で乾いていたようだ。中には車掌と乗務員しかいなかった。お客は私だけ。前述の通り、人が夜な夜な向かう場所ではない、深雪の地、連山の淵である。
18時30分、ついに列車は動きだす。黒煙は留まることを知らずに流れゆき、汽笛は一人旅をいぶかしむかのように、不明瞭な音を響かせた。
こここそ星空の見えるような山中なのには間違いはないが、行く先は更なる深山幽谷なのである。振動に身を任せ、後は何にも気を配ることはないのだが、どうも遠くの山々を臨んでいる間に、沸々と、使命感とも取れない形容し難いものが浮かんできたのだ。
だが、今はそのうちに日が隠れるのを待つばかりである。

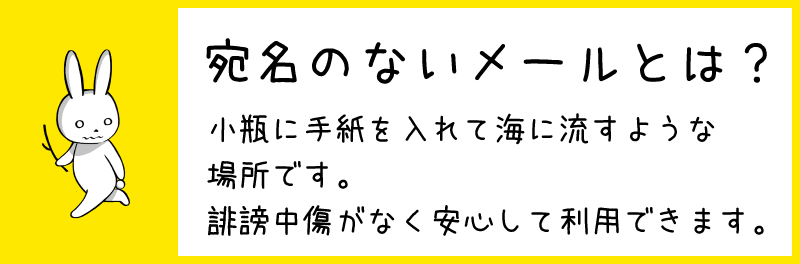


 真野 まの_φ(・ ・✿*
真野 まの_φ(・ ・✿*