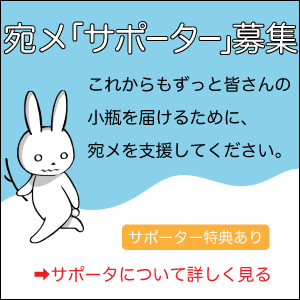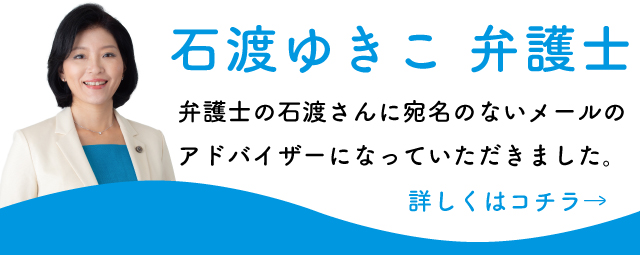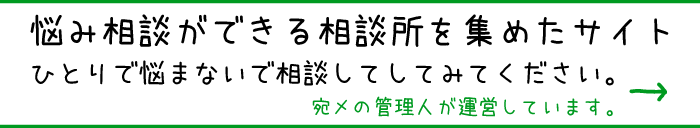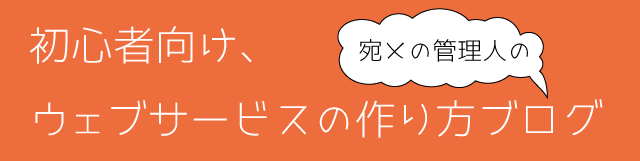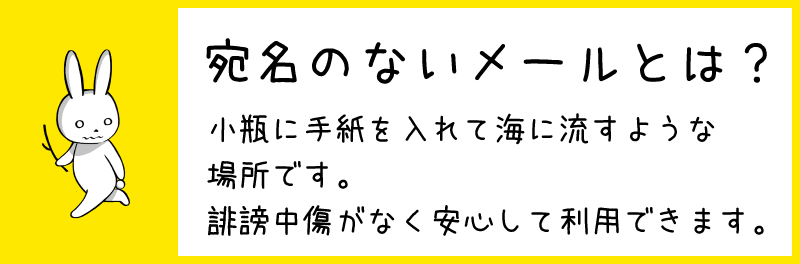

波の音が僕の心を攫っていく。子供の声が遠くで聞こえる。水平線の真上には雷雲が咳払いをしていた。
きっとこんな穏やかな日が人生であるべきなのだろう。常に時間の奴隷、特別重要でないもののためにしがみついて駆けずり回る。そんなものが、この感性や知性豊かである人が送るべき人生なのだろうか。
僕はきっと皮肉れて、不貞腐れて、病んでいる。社会の歯車になりきれてない気がして、上の人間にはがっかりされたようで、直接的な表現をされたわけではないが、きっと陰では酷い笑い物なのだろう。
僕はただ、穏やかに生きたいだけなのに。
努力や、器用さを他人にみせなくとも生きていけるくらいの穏やかさを謳歌したい。だが、求められるものは大抵努力や器用さなのだ。
忙しい人の声には飽き飽きなんだ。どっか遠くの面白みのないフィクションであって欲しいと願わなかった時はない。
また1日が終わろうとしている。
僕は心底嫌気がさした。
『I'll、underworld。』
さぁ、死にたがり諸君この呪文をお試しあれ。
若者の間で今流行っているらしいそれを、僕は思わず呟いた。田舎者には届いていないその噂を僕はどこで知ったのだろう。
高揚する気持ちの思うがまま、僕は海に走り出した波打ち際を踏み潰した途端脚が重くなる。もたつくこともお構いなしに転ぶことさえ恐れなかった。記憶する限りの最後の一歩。僕は空気を失った。苦しんだのだろうか。明日には僕の水死体が発見されることだろう。いや待てよ、僕は何を考えているんだ。僕はなぜ、考えているんだ。
僕の視界は再開した。薄暗い景色、蔦の絡まった木造建築、滴りそうなガラスの照明に黄緑色の扉が照らされている。陰湿な香りが鼻腔を辿り思考に届いた。立ち上がる。四肢の感覚が確かになり僕は気づいた。
『この身体は、誰だ。」

誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項