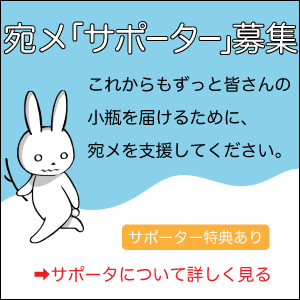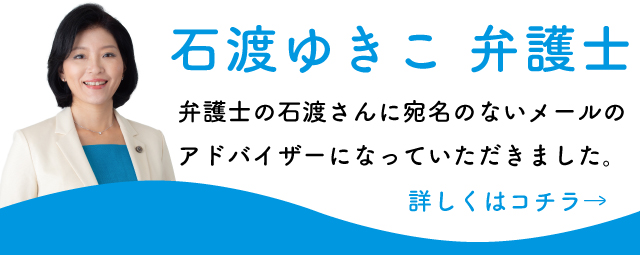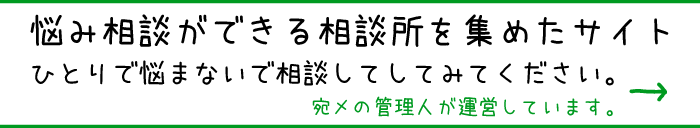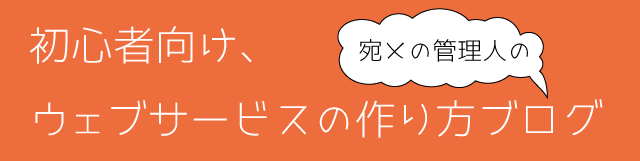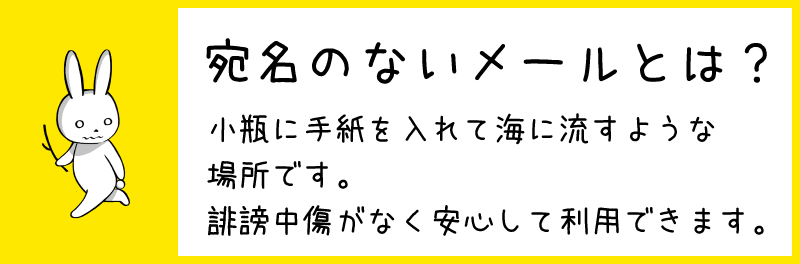

ひとをすきになるほど、距離が近くなるほど、じぶんを知られることがこわくなる。
私をみて! 構って! という気持ちはいつだってあったのに。
深く関わらない、責任とらない半透明で生きてたじぶんはめちゃくちゃさみしくて嫌いで、楽だった。
いざ、ようやく私をみてくれた。
からだを通り抜けていかないまっすぐな目がうれしくてまぶしくて。
だけど話しをすればするほど、経験も考えも浅い、良いかっこしいなじぶんしか居なくて。
せめてからっぽを隠さないでいたいとは思うのだが。
薄っぺらなことばを転がして生きる私を知らないでほしい。
この場所でさえも、見栄えを気にして整えた言葉しか出せない私を笑ってほしい。
そういって繕うことこそ偽物だ、嘘だ、わかっているのに。
どうせもう ばれているのかもしれないけれど。
くれた言葉ぜんぶ、教えてくれた曲のビートも本の一節もぜんぶ、すっかりころんと私のなかにおちてきた。からっぽなこころが、それらみんな まるごと食べてしまうように呑み込んだ。
私にあげられるものがあればいいのに。平ったくてなんにもないから、もっともっととのみこむばかりだ。
いつか去ってしまうのだろう。

誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項

ななしさん
あー、人なんて色々よ
知られたくないならひたすら隠し通せば良いの。
知られたいのならさらけ出せば良いの。
 ちいさな小瓶
ちいさな小瓶
ばれてますよ
って聞いて、なんだろ、すごくほっとしました。
…私は結局なにが怖いのだろう?
じぶんの格好わるさって、わかっているようで目をつむってるんだろうな。
言いたいことはひとつなのに あれこれ飾ろうとする癖。対面して話をするときはちょっとは抜けるようになってきたのだけど、文章はまだまだむずかしい。
お返事、そして拾ってくださった方、どうもありがとうです。
じぶんの言葉でいられるようになりたい。旅を続けます。
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項