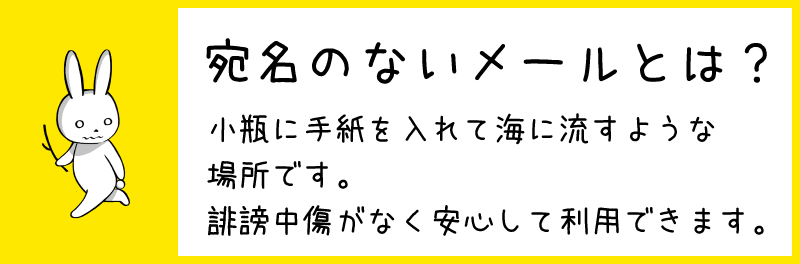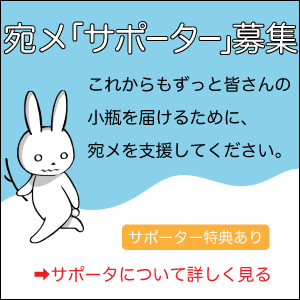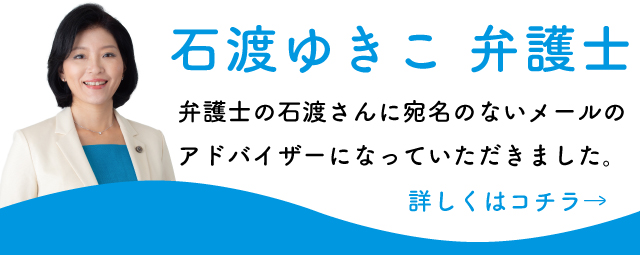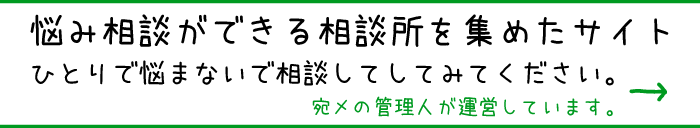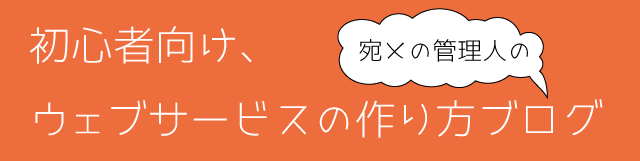不思議なくらい気持ちが凪いでいる。
突然のことだった。
そして、あっという間のことだった。
体のどこも悪くない、認知症と老化以外は。
かかりつけ医にも太鼓判を押されていた。
いったい、このひとはあと何年生きるつもりだろう?
足元をがんじがらめに動けなくなる程までしがみつかれて、この日々は、いつになったら終わってくれるんだろう?
自分が先に死ぬか、さもなければ殺してしまう。
何度そう思ったか知れない。
それが日常だった。
人間って、死ぬんだな。
そうか。
そりゃそうだ。
もう二度と「死ね」と言わなくて済むんだな。
おかしな体勢で家具の隙間に倒れこんでいる父を自分の腕力だけでは横にすることもできず、ただ脈を探り、頬を叩き、耳を引っ張り、名を呼んで、人間としての機能が徐々に失われていくのを、眺めていた。
救急隊が到着するまでの数分間が、生涯最後の、父との対峙だった。
冬、夜明け前、一日で一番暗い時間。
なあ、私は最後まで、逃げなかったよ。
お前はずっと逃げていたけど、私と、私たちと、向き合うことから逃げ続けてきたけど。
よかったな。
もう二度と「向き合え」なんて言わないよ。
安らかだろ。
さみしくなんかないだろう?
思い残すことなんか。
私はないよ。
悲しみも。
ああ、
やっと終わった。