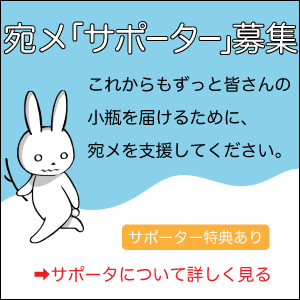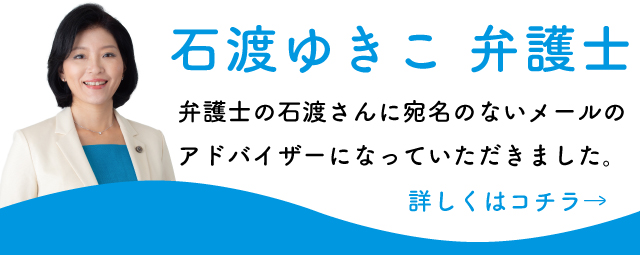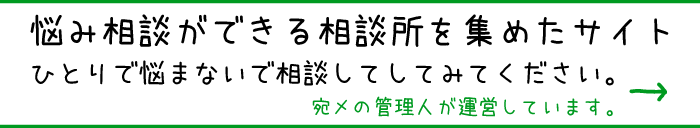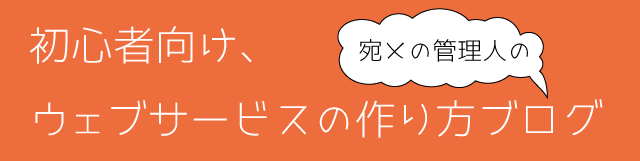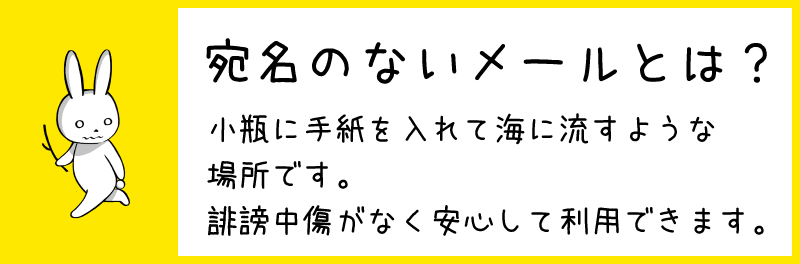

遠方からの帰り、冬の到来により日照時間は短くなっていた。方向と路線のみを正確にし、あとはなんとなく感覚で電車に乗った。ちゃんと目的の駅まで行くのか、不安にはならない程に私は楽観的な人間だ。
普通電車に乗ったはずが、なかなか車内案内が聞こえてこない。妙に停車駅間が長いのだ。行きしに読み切った文藝部の作品は、もう一度読む気になれなかった。
夜なだけあり、車窓の外は黒く、遠くの田舎道を走る僅かな車の明かりが通り過ぎるのみである。
不規則に軋む車両の雑音に慣れてしまうと、爺の咳払いが響いた。
震動する車両に明るいこの空間、私はどこか浮世離れた感覚を覚えた。
やたらと目の合う斜め前の男、複数の車両を行ったり来たりする迷彩の爺。暖かすぎる座席。
再度、寒いであろう車窓の外に目を向ける。映る不安げな私の表情と、目の合う男が、窓枠に飾られているのが観えた。
待ち望んだ車内案内は無機質な女の声、停まった駅はひと気のない白い照明で薄明るく浮かび上がっていた。
心ごと、電車に揺られる。

誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います
▶ お返事の注意事項