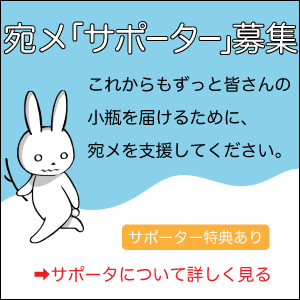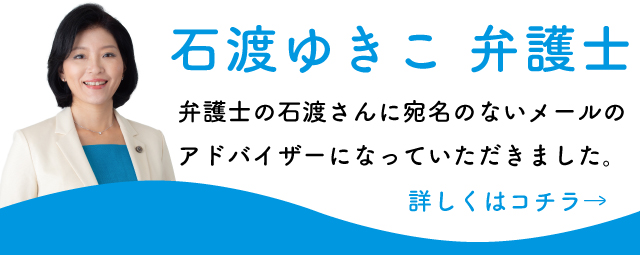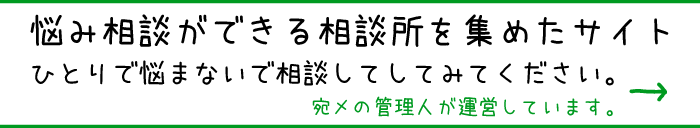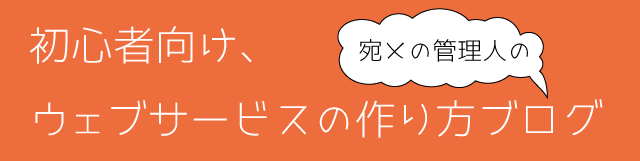〜瑠唯 視点〜
『瑠唯さぁ、ロケラン持ってない?』
「どんな質問だよ」
『ぶっ放したくてしかたないんだよ〜!』
「持ってるわけないでしょ。思考回路、猟奇的すぎ。」
電話をかけて開口一番、明來は変なことを口走る。だいぶイライラしてるみたいだ。
『クソジジイが電話かけて来てさぁ。もう話すことねえよっつって切ったんだよ。』
「え、ルール的にだめじゃないの?」
『あいつ、ルールの抜け穴くぐるプロじゃん。』
「じゃんって言われても…。まぁ、明來の話聞いた感じそうだね。」
『わかってくれた!さすがは我が親友!』
「声でかい。耳痛い。」
明來は、中学に進学してからできた、ただ一人の親友。
第一印象は最悪だった。校則を平気で破り、先生に口答えをし、遅刻なんて当たり前。僕の大嫌いな人種。
でも、その印象が変わったのは、5月の職場体験のときだった。
僕と明來のいた班は、書店で働いていた。明來は、お昼休憩のとき毎回いなくなり、店長さんを困らせた。
早めに昼食を食べ終えた三日目、僕はバックヤードで座り込んでいる明來を見つけた。
『どうしたんですか。』
『え?あー。うち、弁当ないからさ。』
『忘れたんですか?』
『そういうわけじゃなくて。てか、敬語やめて?話しづらいからさぁ。』
そういって、明來は僕にいろんなことを話してくれた。
弁当の材料を買うお金も、作れる人もないこと。父親が母親にDVして、離婚手続き中なこと。年齢詐称してバイトしていること。お金がなくて学校をやめなければならないこと。
僕は掛ける言葉が見つからなくて、急いで脳内の言葉の引き出しを漁る。
すると、明來は急に笑い出した。
『焦ってんのわかりやすっwなんか敷居高そうな感じしてたけど、意外とそうでもないじゃんw』
そして、笑い終えると、明來は僕に向き直った。
『瑠唯、だっけ?あのさ、友達になってくんない?』
「設楽先生が様子見てこいって。」
『もー。しーたんうるっさいな〜。』
「…設楽先生のこと、しーたんって呼ぶのやめなよ。」
『だって、中退したうちにとっては先生じゃないじゃん?』
「まあそうなんだけど。」
『あ、離婚手続き終わった話ってした?』
「先週聞いた。」
『じゃあもう話すことない!終わり!』
明來がそのままの勢いで、電話を切ろうとする。
「あ、ごめん。個人的にちょっと相談あってさ。」
『お、どした〜?』
「…進路のことなんだけど。」

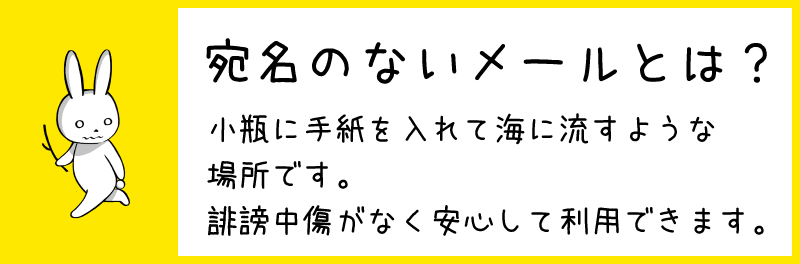


 nanaha.
nanaha.