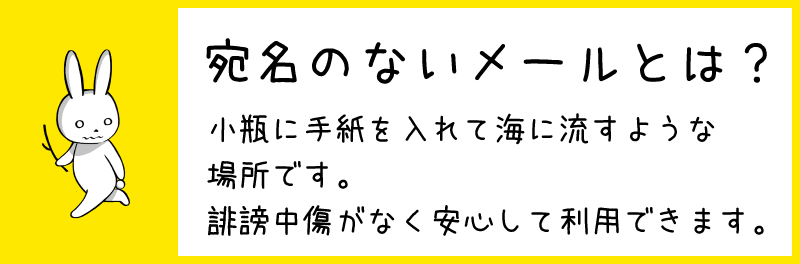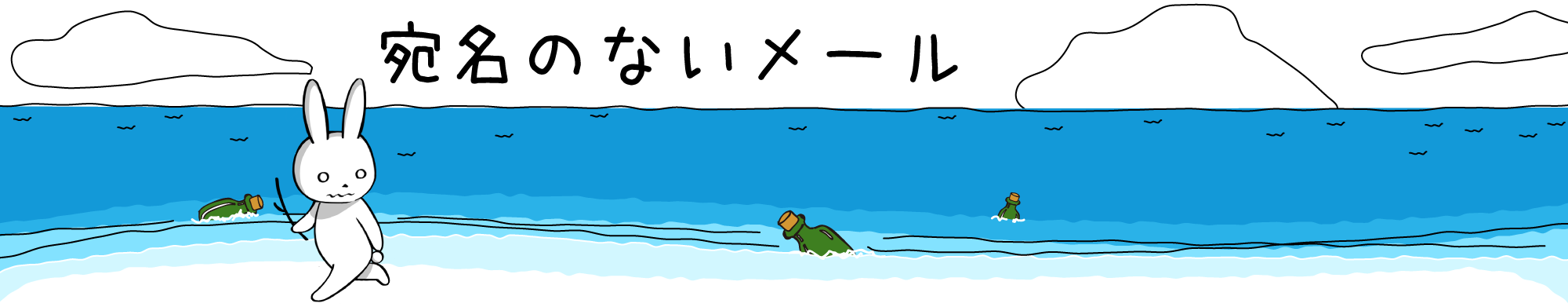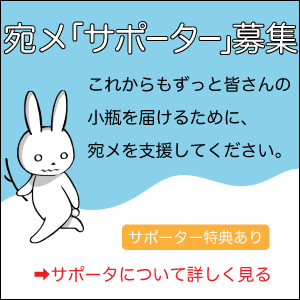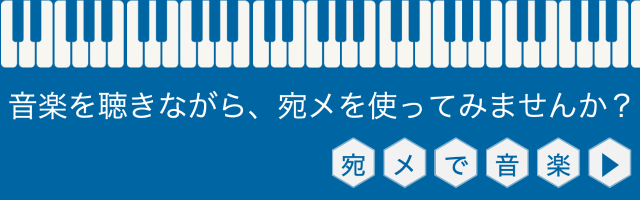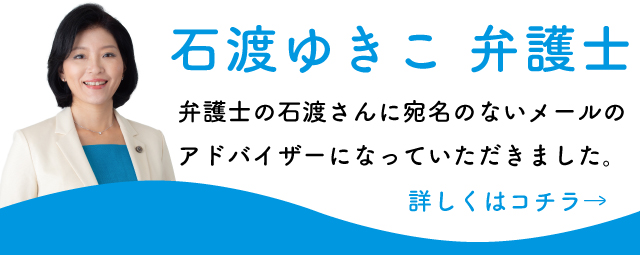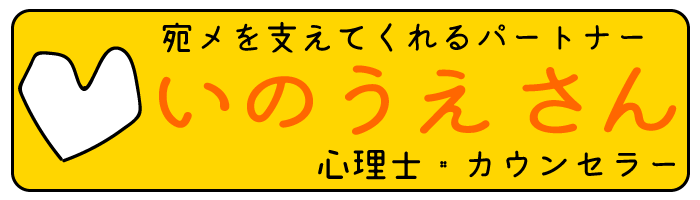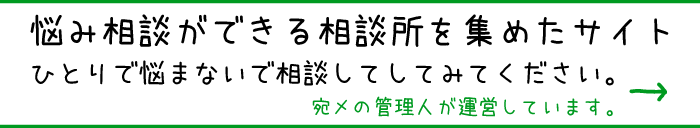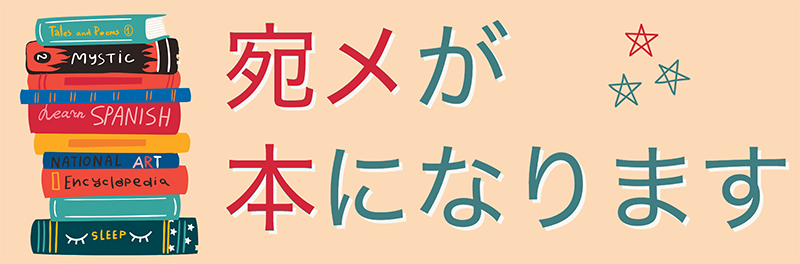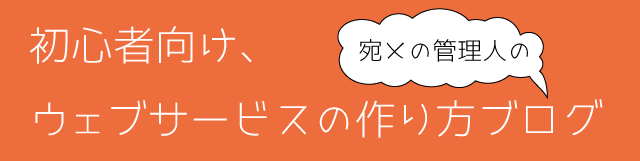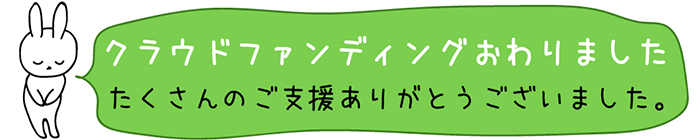小瓶主さんからのお返事
ななしさん、
こんにちは。
花粉症がひどくて参ってます。涙
僕の母校はかなり自由な校風だったので、英検の団体受験などの斡旋もなかったし、個人の意思に任されてましたね。
英語が得意なやつらが仲間内に何人かいて、普段はサッカーやってたりバスケやってたり。
で、サッカーやってる方が僕と同じ受験回で準1級を受けて、残念ながら面接に落ちたと聞きましたが、そいつは後に交換留学でオーストラリアへ行きました。
それを見送った僕は土曜日の放課後に教頭から呼ばれて、「部活の前にお昼でもどうですか?」なんて言うので、ファミレスに行ったんです。
そしたら、豪の協定校からやってくる生徒の buddy を君に引き受けてもらいたい、と。
(心の声)
「こちとら吹奏楽部のキャプテンと生徒会の副会長の二足の草鞋を履くのが内定してるのよ? てか準1級なくても良いよね?」
そんなことを脳内でブツクサ言いつつも、教頭から直々に頼まれてしまっては NO とも言えず。
三足の草鞋を無理やり履いて一年間過ごしました……。
おっしゃる通り同級生の中にもいろいろ居て、英語には興味ねーやっていうやつらも少なくなかったです。
中高一貫校ってこともあって、一風変わった教育だったんですよね。
教員は皆、何かしらの専門領域を持ってる人たちで、高校2~3年生ではゼミナール形式の授業もあったので、生徒それぞれの得意分野や尖った部分を発揮できる環境ではあったと思います。
僕の学年は意外と議論好きなやつらが集まってたので、小委員会とかで文字起こしなんかしてても面白かったですよ。
IT の発展、充実はたしかに、学習環境・意欲の向上に資するものだと思います。
自身の英文ライティングの成果を AI に見てもらったり、条件を与えて修正してもらえたりするなんて、21年前には考え付かなかったことです。
当時の機械翻訳なんて本当にいい加減でしたから。
これは僕の肌感覚でしかないのですが、外国語の習得はセンスの有無に左右されるところが大きいでしょうから、「あなた向いてるよ」と言ってくれる人々の存在がとても有難かったですね。
そういった意味では、自分の頑張りだけではなくて周りのいろんな人達が育ててくれたということだと感じてます。
英語の習得は生涯学習として取り組まれたら一番いいと思いますし、資格取得についてもご自身の納得行くまで突き詰めて行かれたらいいと思います。
あとは資格ではどうにもならない部分、僕の場合で言えば病院における外国の方との面談、そこで求められるリテラシや資質・背景理解力などは、英語力という強固な岩盤の上に育てていかなくてはならないものなので、とにかく日々前進っていう感じですね……。
僕の現在位置より
Mar 27, 2025 at 10:16 pm